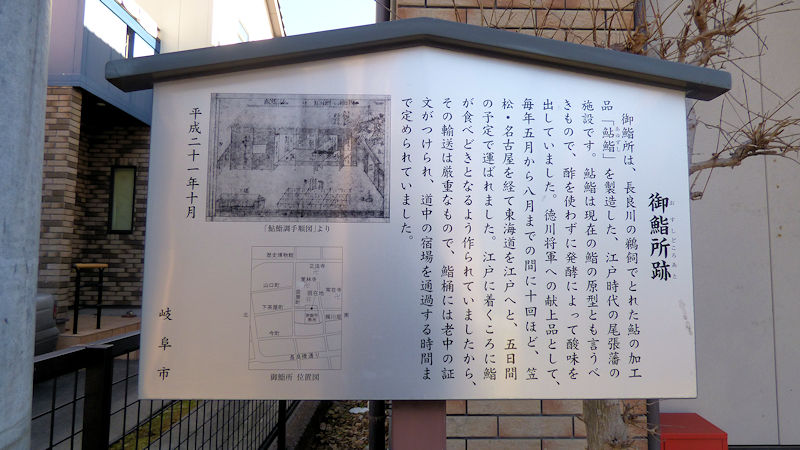>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<
加納 > 加納

随分と 来たよでまだまだ お膝元
若宮町通り。
「これは、すごいね。通りの正面、街並みの谷間に、伊吹山。」なかなか、かっこいいよね。
電柱も、電線も、ごちゃごちゃしてなくて、すっきりしていて、いいね。「信長公、町の名前を、よく、伊吹に、しなかったものだね。」 うん、説得力ある風景だよね。
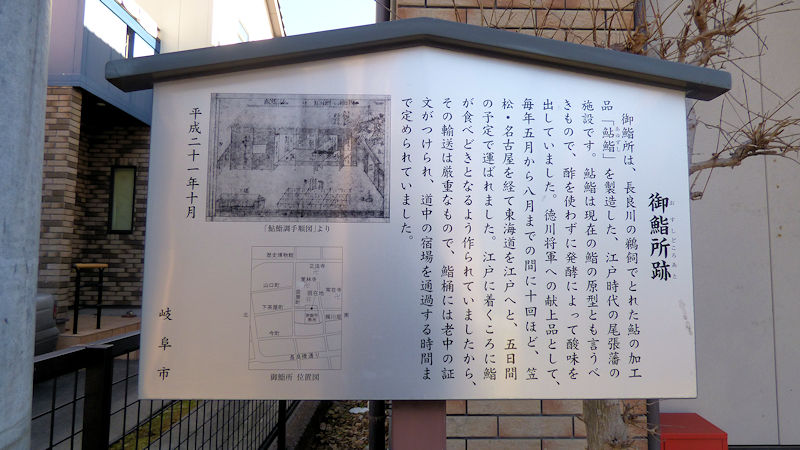
名前だけ お寿司どころに 店は無し
御鮨所跡。
「美濃路を歩いた時に、鮎鮨街道って、あったよね。」あったね。清洲の北、四ツ家追分で分岐してたよね。「その街道の終着点が、ここ?」
そう。正確には、ここで製造された鮎鮨を、江戸の将軍家まで届けた道の、出発点だね。酢を使わず、発酵させて、ちょうど江戸に着く頃に、食べどきになるようにされていたようだよ。
「わざわざ、ここから? そんなに美味しかったのかな?」たぶんね。毎年五月から八月の間に、十回程度、運ばれたようだよ。「へ〜、食べたくなってきたね。」

小手先から 先の先まで 描きつつ
竹中半兵衛。
「我らが軍師、半兵衛さまだけど、この花押は、真似できないね。無理。なんて書いてあるの?」
千年鳳…だとか。「何?それ?」鳳、鳳凰は、聖人のような天子が出た時に、出現する。つまり、そのような世の中を目指す。千年の平和への願いが、込められているそうな。「ほ〜、さすがわ、軍師さまだね。」

大それた 夢をそのまま 実現し
木下秀吉。
後の豊臣秀吉だね。「秀吉さんの花押って、木下って名乗っていた時から、これだったの?」すわぁ〜、どうなんだろうね。
「これは、秀吉の秀の字だよね?」いやいや、秀吉を、しゅうきつ、と、読んで、その頭とお尻の字から、しつ、漢字で、悉、を、もってきたみたいだね。
「悉って?」ことごとく、だね。この字からさらに、悉国平定、つまり、すべての国を平定する、と言う意気込みが込められているそうな。「さすがわ、天下人だね。」
若者の 斬新さには ついてけず
森蘭丸。
森蘭丸だね。「背が高くって、武勇にすぐれ、本能寺に散った美男子。」でも、結構、時代が下ってからのイメージ像みたいだよ。「そうなの?」
十二歳ごろから信長さんの小姓となり、本能寺の変の頃には、五万石の大名だったとか。「若くして大名、やっぱり、かっこいいね。でも、この花押は? 何?」
う〜ん…、史上はじめての顔文字とか?「は〜?」こんな感じ。°" °" ( _ ) ‼︎「目が飛び出てるってこと?」信長さんが、こう言ってるけど、私もビックリしてるんです、ってな感じ。「ほんまかいな??」m(_ _)m。

大平に なるまでのこと 見てるかな
織田信長。
「信長さんの花押も、読めないね。」これは、麒麟の、麟、の字だそうな。「麒麟がくるの、麒麟? あの大河ドラマで言っていた事って、信長さんが願っていた事?」そうだよね。笑かそうとしてたのかな?
麒麟は、大平の世に現れるとされる聖なる獣。その大平の世の中の到来を願って、この花押を使っていたのなら、やっぱり他の武将とは、ひと味、違うね。

見開いて いるのかどうか 見るほどに
岐阜大仏 賓頭盧尊者。
賓頭盧さまだね。「顔の表情が、よく分かんなくなってるね。」 撫で仏さまだからね。数え切れないくらい、たくさんの人に、撫でられてきたんだろうね。
「目は、ひらいているの? 閉じているの?」 う〜ん、どちらとも、とれるね。
心の目、心眼で物事を見ている像を作れって言われたら、この像なんかは、その最高傑作じゃないかな?

大仏に 覗き込まれて 縮こまり
岐阜大仏。
「いや〜、鎌倉でも、奈良でも、大仏さまには、おめにかかっているけど…、こちらの大仏さまは、でっかいね。」 そうだね。なんか、覆い被さってこられるような、圧倒的な迫力を感じるよね。
「よくよく見ると、やっぱり、前屈みになっておられるせいかな?」 そうだね。デザインというか、設計した人、すごいね。
合格の サインだろうか OKを
岐阜大仏。
「大仏さまが、OKサインを、出しておられるけど? これって、心の中まで見とおして、この者は、清い心だから、OKって、おっしゃってるの?」
これ、OKサインじゃなくて…、う〜ん…、思惟手…かな?「思惟手って?」 う〜ん、考え事をされているのかな。「なにを?」 う〜ん、この人を、どうやって救おうかな?とか?
「それって、OKじゃないってこと? しかも、どうやって救おうかって考えるのは、救いようがないってこと?」 笑。m(_ _)m。いやいや、悩み、願いを聞いて、一緒に考えてくださるんじゃないかな。でもって、誰が見てもそうだけど、OKってね。
軽いかと 思える張子も 念ずれば
岐阜大仏。
「張子って?」 この大仏さま。「そうなの?」
真柱を立て、木材で骨組みを作り、竹を編んで大仏さまの形になっているようだね。「表面は?」
編んだ竹の上に粘土を塗って、その上に美濃和紙、漆、金箔が貼ってあるそうな。
「なんか、とっても、かる〜い、イメージだね。」 そんなこと、ないよ。貼られている美濃和紙だけど…。「和紙が?何か?」
一切経、法華経、阿弥陀経、観音経等の経典が書かれた美濃和紙が、ご住職の読経のもと、一枚、一枚、貼られている。その経典の数は、四万巻に上るとか。
「なんと…、大仏さまの表情とは裏腹に、念の込め方と言うか、すごく重いね。」 重いけど、お優しい顔だね。ホント。

時経てば 誰もいない お堂しも
岐阜大仏 五百羅漢。
おっ! 目が慣れてきたら、大仏殿の中、誰かと言うか、たくさん人がいるね。「ホントだ。」
五百羅漢だね。こっちが、勝手に気づかなかっただけだけど、これだけの人数が、音もなく静かに、時間差をおいて、登場するのは、感動するね。
地震にて 数は減れども 五百羅漢
岐阜大仏 五百羅漢。
「五百羅漢って? 言葉の響きだけからすると、力強くって、最強の集団みたいに、思うんだけど?」
釈迦の五百人の弟子たちだね。でも、明治の濃尾大震災で、お堂は大丈夫だったけど、壊れた羅漢さんもあったとか。

半兵衛の 懐刀の 稲荷さま
三光稲荷神社。
「半兵衛って?」 軍師、竹中半兵衛!「なんの関係?」
ここのお寺さんは、竹中半兵衛の屋敷跡に建ったそうな。「そうなの?」
しかも、このお稲荷さんは、お寺が建つ前からあったとか。「じゃぁ、半兵衛さんの屋敷の中のお社だったの?」
なんか、そう思うと、知恵の神様のように思えてくるね。「そうかぁ、奇抜な作戦は、このお稲荷様が、考えていたのか?」 いやいや…。

姿なし ねこにかまくら 溶けるだけ
妙照寺。
猫の、かまくら、って、初めて見たね。主役の、猫ちゃんが、いないけど?中に入って、こっちを見てくれないかな?
「でも〜、これ〜、本当に、猫の、かまくら?」 犬かな?「いや、そうじゃなくて。」

板垣も 自由も死せず 永遠に
板垣退助像。
「これは、誰がどう見ても、板垣退助さんだね。」 そうだね。そうとしか、見えないね。「なんで、ここに、おられるの?」
ここで、暴漢に襲われて…。「えっ? 板垣死すとも自由は死せず、って、言ったのは、ここ?」 その通り。
「じゃ〜、この像は、供養の像でもあるわけ?」 供養? なんか、勘違いしてない? 板垣さん、暴漢に襲われたけど、死んじゃ、いないよ! 事件当時、45歳くらい。板垣さんは、82歳くらいまで、長生きされてるからね。「そうなの? 学校の先生、ちゃんと言ってたっけ??」 いやいや、ちゃんと、聞いてた?

板垣が 自由にあらずば もう一度
板垣退助像。
板垣死すとも自由は死せず、の、言葉は有名だけど…。「テストに出たことはないけどね。」 おいっ! でも、襲撃犯が、出所後、板垣さんに謝罪に来た時の、板垣さんの言葉がすごい。「何? なに?」
自分は、昔も今も、常に国家のことを考えて行動し、自分こそが国家の忠臣であると思っているとした上で…。
もし、今後、退助が行うことに対して、いかにも国家に不忠であると思われることがあったなら、斬るも、刺すも、君の思うままに振る舞われよと。
「すごいね。常日頃の覚悟が、違うね。」

足元に 広がるパノラマ 閉所から
ロープウェイ。
「ロープウェイだね。」 山頂まで、った四分で、行けるそうな。「お城まで?」
いやいや、直結はしてないよ。山頂駅まで。駅からは、程よい程度の、登り道があるから、ロープウェイを使いながらも、登った感も味わうことができるようになってるね。「いいね。」
でも、なんか、よく見ると、混んでるね。「満員だね。」 歩いて登ろうか?

整備さる 天下布武への お城へと
登山口。
公園からの登山口だね。「いいね、この、案内板。」
なんか、天下布武のお城の、品格を感じるね。

猛々し 織田家の戦士 今もなお
猪の看板。
「戦士…って、イノシシのこと?」 そう。廃城になってから、400年を越えているけど、今なお、お城を守っている戦士。しかも、親子代々。
「う〜ん…、でも、看板には、絶対にエサをやらない、って、書いてあるから、戦士っつ〜感じじゃないでしょ?」 ちょっと、無理?
「それよりも、エサをあげるっていう、この街の人の方が、つわもののような気が…。m(_ _)m。」
ひょっとしたら、思わずエサをあげたくなるほど、かわいいのかもね。「なるほど。」

選ばれし 者のみ登れる 天下道
馬の背。
「お城に登る道は、このみちだけ?」 いやいや、主だった道としては、四つあるみたいだね。大手道、水手道、百曲がり登山道、馬の背登山道。
「今、進んでいるのは?」 馬の背。その名前の通り、尾根筋を、直線的に登る、一番険しい道だね。
「いいね。難攻不落のお城の、一番険しい道。登った時の、達成感が格段にいいだろうね…、でも、そんなに、キツくないような?」 まだ、導線だね。「さいですか。」

老人と 幼児でも天下 取れるのに
馬の背。
「案内板があるね。老人・幼児には無理です、って、言い切ってるね。」 まぁ、声を大にして、書いてあるから、無理なんでしょうね。でも、よくいるよね。忠告を無視して行って、迷惑をかける人。
「そうだね。じゃ〜、引き返すの?」 えっ?なんで?「ひょっとして、旅人さん、自分がどのカテゴリにいるのか、分かってない?」 おいっ!

選ばれぬ 者は無理です 天下道
馬の背。
「馬の背、って、こう言う道なんだね。」 いいね。まぁ、岩登りじゃないんだけれど、足だけでは危ない、手袋はめて、所々、手をつきつつ登るって感じかな。
「小学校の高学年くらいなら、大喜びかな?」 そうだね。でも、直線的に登るから負荷が大きいし、一気に進んじゃダメだね。「一区切り登るごとに、振り返って、達成感を味わい、次の一区切りを眺めて、ワクワクする?」 その小まめに息を整えながら、少しづつ、楽しく登るのがいいね。

飽きつつも 戻る選択 余地は無く
馬の背。
「もう、いいね、馬の背。」 そうだね。手をついて登るような岩場、もう、何ヶ所目?って、感じ。
「だんだん、写真も、撮らなくなってきたね。笑。」 まぁ、いまさら、戻れないよね。「そう。上りは、なんとか、行けるけど、下りに関しては、幼児と老人は、絶対、無理だね。ホント。」

どうやって 揚げたか積んだか 山の城
岐阜城。
ちょっと、ここで立ち止まって、行き来する人の声を聞いてみたんだけど…。「息を整えるのに、へたり込んでいたら、どうしたって?」 おいっ!
この石、どうやって、ここまで、運んできたの?
この石、どうやって積んだの?
このふたつ、まったく同じ会話を、四回くらい、聞いたかな。「う〜ん、まったく同じ、感想だね。」 と言うか、馬の背を登ってきたら、感想は、それしかないよ。

遥拝す 白山権現 南下して
権現山。
「あれは〜、見覚えのある稜線だね。」 そうだね。伊奈波神社の拝殿のあたりから見たかな。「河渡宿は長良川の堤防からも見たよね。なんて山?」 おいっ!
権現山だね。1157メートル。「なんで、権現山?」 白山権現の祠があるかららしいね。濃尾平野からだと、総本社の加賀国の白山は、見えないけれど、この権現山は、よく見えるからね。ちなみに、山頂からは、白山が見えるそうな。「なるほど、遥拝しとこ。」

薮にしろ 雪になっても 道はなく
花房山。
この山も、先に見てるね。「花房山だね。」 1189メートル。「薮かきわけて進む山だっけ?」
そう。でも、雪の季節は、雪で藪が抑えられて、楽なんじゃない?「いやいや、おんなじようなもんじゃない? たぶん、みちなきみちを行くんでしょ。加えて、寒いんじゃねぇ。」 やっぱ、無理かな。

雷の 子供の遊ぶ お山かな
小津三山のひとつ、雷倉。
「えっ?そうなの?」 いやいや、勝手に、思っただけ。「おいっ!」
でも、ちょっとだけ顔を出してるところなんか、そんな感じしない?「まぁ、そう言われればね。」
残っている伝説でも、落ちてきた雷を捕まえて叱ったとか、天狗が天に向けて、放り投げたとか…。「なるほど…、雷神様と言うよりも、わんぱくな雷の子供って雰囲気だね。」
でも、よくよく考えたら、そんなことする里の人の方が、すごいよね。「落ちてきた雷、つかまえてんだから。笑。」

はるかかな 日本海から 覗く山
能郷白山。
「えっ? あそこは、日本海側になるの?」 分水嶺だね。岐阜県揖斐川町と、福井県大野市の境にそびえる、1617メートルのお山だね。
この、お山、岐阜に来て、はじめて知ったね。「まえ、どこで見たっけ?」 う〜ん? どこだっけ? 美濃路は木曽三川のいずれかの堤防の上? 電車の車窓からだろうかね。「すごく目を引いたけど、謎の山だったよね。」
濃尾平野から見える山で、一番最後まで、雪をいただく山だそうな。「冬将軍の住む城?」

ちさければ 威厳も小さき 信長公
黄金の信長像レプリカ。
「これ、どこで見た?」 何を言っているのやら。駅前にあったでしょ!「あ〜、あれのミニチュア版?」 みたいだね…。「でも、大きさは違うけど、見上げていた像を、見下げて見ると、なんか、違うような気がするね。」
う〜ん、やっぱり駅前の像のように、桁違いの大きさの方が、威厳があっていいかな。「確かに、過去の信長公が出てきたどらまでも、チンチクリンだったり、したら、怖さを感じないものね。」 それ、誰のことをいってるの?

マント着る 先にも後にも 誰もなく
銀箔押南蛮具足。
「いゃぁ〜、本当に、マントしてたんだね。」 そうだね。テレビや映画で、信長さんの奇抜さを表現するためのデザインだと思っていたけど…。「根拠があるんだね。」
でも、当然、信長さん以前に、こんな格好していた人はいないけど、家臣も含めて、真似する人は、誰もいなかったのかね。「確かに、流行しても…、とは、思うけどね。」
流行していたら、日本の文化、変わっていたかもね。「侘び寂びは、無かったんじゃない? 笑。」

天空へ どちらが先に 届くかな
名古屋駅超高層ビル群。
「なんか、あそこに目を引く、ゴツゴツしたビルふたつ、あれは何?」
ふたつに見えるけど、たぶん、左側は三つ、右側は五つの、ビルが合体したものだね。「合体?」
左が、大名古屋ビルヂング、ミッドランドスクエア、モード学圏スパイラルタワーズ。
名駅通りを挟んで右側が、名古屋ルーセントタワー、JPタワー名古屋、JRゲートタワー、JRセントラルタワーズのオフィスタワーとホテルタワー。
その右下あたりが名古屋駅…かな。たぶん。「見た感じ…、右も左も、同じ高さ?」左の方が、約2メートル高いね。「細か!」その左側が、なんと、247メートル。
「へっ、へっ、へっ。たった、247メートル?勝ったね。」えっ?何が?「ここ、岐阜城は329メートル!」何を自慢しているのやら...。

民話なる 山から見れば 現実が
御井神社。
「なんか、可愛らしい山というか、丘があるね。右側の山。てっぺんに、木が二本。あれは?」
う〜ん、たぶん、各務原市の三井城跡、御井神社奥之宮…かな?よく見ると、木は二本じゃなくて、数本あるみたいだけど、いいね。昔むかしの、その昔話に、出てきそうなお山だね。「そうだね。どんな世界が広がっているのかな?行ってみたいね。」でも...。「でも?」
あの山は、陸上自衛隊岐阜基地の戦闘機の離発着が見られることで、有名な山だそうだよ。「なんと。こちらから見たら、民話的な世界で、向こうからみたら、国防最前線の超現実世界?」

おそらくは あちらから見ても ちさき城
犬山城。
「あのお城は?」 う〜ん、おそらく…、犬山城…かな?「犬山藩?」いやいや、尾張藩の家老、成瀬さんの城だね。「ご家老?」そう、と言っても、三万五千石で、城持ち、幕府からの付家老をだからね。
「向こうも尾張藩、ここも尾張藩だよね。尾張藩って、お城、いくつもってたの?」たくさん…と、言いたいところだけど、名古屋と犬山のふたつかな?他の家老さんたちは、陣屋だろうし、ここも含めて、あとは、廃城になってたと思う。

モデル立ち 中央アルプス オールスター
中央アルプス。
「あれは…中央アルプス?」 そう、金生山の参道からは、左側の三分の一しか、分からなかったけど、きれいに見えてるね。「オールスターだね。山の名前、分かる?」
雪のいただきで、一番左の少し低いのが、麦草岳。続けて右の方へ、木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳、三ノ沢岳。ここまでが、金生山で見えてた山だね。
雪が深く切れ込んでいるところから、檜尾岳、熊沢岳、東川岳。
稜線が切れているように見えてる奥の山が、空木岳、赤梛岳、南駒ヶ岳、仙厓嶺、越百山。
「すごいね。いずれも、2600から2900メートル代の山だね。拝んどこ。」 登らんのかい!

本当に あるよな気のする 御嶽山
御嶽山。
「本当にあるようなって、何?それ?」 いやいや、今まで見てきた御嶽山は、近くの山々の上の空を、じっと見ていると、浮かんでくる感じの、幻みたいな山だったからね。「確かに…。うっすらと、絵に描いたような感は、あったね。」
それに、今まで大きなひとつ塊の山だと思っていたけど、峰が幾つもあるんだね。「峰の名前、分かる?」
う〜ん、一番左の雪の頂で最も低いのが、継子岳(ままこだけ)…、かな…。2,859メートル。
右となりの少し高くなっているのが、摩利支天山(まりしてんやま)…、たぶん…。2,959メートル。
その右、へこんでいるところ、手前に尾根が延びていて、これが継母岳(ままははだけ)…、おそらく…。2,867メートル。
さらにその右、ふたつピークがある右側が、最高峰の剣ヶ峰(けんがみね)。3,067メートル。「左側は?」 向こう側にある火口湖の一ノ池の外輪の尾根になるのかな…。「こっちの方が、高く見えるけど?」 う〜ん…、手前にあるからかな…。
そのふたつのピークから、右下の方向に、雪がまばらなように見える沢があるのが、地獄谷。噴煙をあげているところかな。
そして、一番右端が、王滝頂上(おうたきちょうじょう)、2,859メートル。全部合わせて、御嶽山。「ホント、巨大な、お山だね。」

また違う 世界が少し 顔を出し
乗鞍。
「御嶽山の北と言うか、さらに奥の方に、白く続く山々があるね。あれは?」
う〜ん…、真ん中あたりで、手前の山と重なって切れ気味のところがあるけど、それも含めて、それより右側が、乗鞍だろうかね。たぶん…。
「どれが乗鞍?」 全部、乗鞍。「??」 あの辺の山々の総称だね。一番高いのが、剣ヶ峰、3026メートルだね。
「3000メートル越えって、やっぱり、近寄りがたい山?」 整備されてるから、誰でも行けるよ。2700メートルまで、バスで行けるからね。極端な話、普段着でも、大丈夫。「そうなんだ。異世界だと思ったけど…。」 異世界が、体験できる世界かな。

続きでも 近寄りがたい 世界かな
穂高。
「さっきの、左半分の山々は?」 う〜ん、穂高かな?たぶん。乗鞍からしたら、北東に離れているから、少し低く見えるけど、3000メートルの山々だね。「穂高って、あの上高地の山々?」
そうだね。かなり、いい加減だけど、一番右にプチってあるのが、前穂高、そのひだりで、ふたつコブみたいなのが、奥穂高、涸沢岳と北穂高が合体したやつ。「合体?」穂高の尾根筋方向に見ているから、穂高の山々がすべて合体したような山のかたちになってるのかな。
その左にまたプチってあるのが、南岳、そして、一番左、プチプチプチって、三つあるのが、中岳、大喰岳、そして槍ヶ岳…かな。
「プチ…なんて言ってるけど、今、あげた山って、すべて、3000メートル越えてるんだよね。凄まじいね。」

槍よりも 剣よりかは 市女笠
笠ヶ岳。
「一番、奥にある山、むちゃ、とんがってるけど、何てやま?」 そうだね。すごく、とんがってるよね。山容からすると…。「なんとか槍ヶ岳? 何とか剣岳?」
ん〜、たぶんだけど、笠ヶ岳、かな?「笠…? 笠と言えば…、三度笠?」渡世人がかぶってるやつ?
「鳥追い笠?」阿波踊りの?
「天蓋?」虚無僧の?
「陣笠?」大石内蔵助が討ち入りの?
「一文字笠?」大名行列のお供の?これ、平だし。
「深編笠?」柳生十兵衛の?雰囲気、だいぶん近いね。
「市女笠?」平安時代の上流階級の女性が使ったやつ? 真ん中が、尖ってるね。これかな?「確かに…って気はするけど、誰が命名したのかな?」

大地より 空より大きな お城かな
岐阜城。
「でっかい、お城だね。」そうだね。下から見上げていた、山を含んだお城よりも、登ってきて、ここから見るお城の方が大きいね。「屋根だけだけどね。」

近くより 遠くを望む 天下城
岐阜城。
「まさに、天下国家に、ずっと先の将来に、思いを巡らせる、お城だね。」

仏舎利の 代わりに祝いの こころをば
三重塔。
「先ほどのロープウェイのバックにあった三重塔。これは、岐阜城の守護のためのお寺さん?」いやいや、大正天皇の即位を祝って、建てられたらしいね。
「なんと…。それじゃぁ、塔だけがあるの?」そのようだね。「だから、ロープウェイも、近くに設置できたんだね。」
確かに。ロープウェイに乗ったら、塔の上から下まで、見れるんだね。「お城から、降りてくる時、ロープウェイ、乗ったけど、どうだった?」えっ?反対側見てた。「おいっ!」

同じよで 同じ人には あらずして
若き日の信長像。
う〜ん、天下布武のステージに進んだお城をバックにして、この人馬肉体美の信長像は…、う〜ん、なんか違和感あるね。「じゃ〜、どこに設置したらいいの?」
そうだね…、例えば、井の頭公園とか?「もう、置いてあるし!」あれは、何で?「そら〜、同じ作者の長崎平和祈念像と同様、肉体美における平和、戦さのない世を願ってでしょ。」
もう、あるのか…。そしたら、兵庫県庁舎とか?「あ〜た、それ、絶対に、調べて、言ってるでしょ‼︎」m(_ _)m。

廃城と なりても町は 拡大し
川原町。
このあたり、木曽川に面する川湊、木曽の木材、美濃紙、茶、関の刃物など、さまざまな物資の集積地として、栄えたようだね。「お城は廃城になっていて、尾張藩領だったんだよね?」
そう、でも、人口は、中山道の中でも大きかった加納宿の約二倍はあったようだよ。「そうなんだ。お城が無くなっても、町は発展していったんだね。」

まぶしきや 陽を背に受けても 白き像
篝火の像。
「これは、誰?」川端康成さんと、その初恋の人、伊藤初代さん…かな?「初々しいね。」
う〜ん、ただ単に、突っ立ってるだけなのに、雰囲気出してる像ってのも、珍しいね。「総合芸術?」

おもしろうて やがても気づかぬ 芭蕉句碑
(写真は、鵜飼観覧船事務所)
「何?それ? 川端さんの像に気をとられて、芭蕉句碑には、気づかず、帰っちゃった?」そう。m(_ _)m。碑の句は、これ。
おもしろうて やがて悲しき 鵜舟かな
(松尾芭蕉)
「これは、分かるね。イベントの後の静寂。」そうだね。
弟子「師匠、鵜飼、面白かったですね。」
芭蕉「面白かったね。」
弟子「師匠、一句、できました?」
芭蕉「…(か、考えてなかった。)。」
…てな、感じ?「そう、そう。それだけ、楽しかったってこと?」でも…。「でも?」これって、謡曲、鵜飼、を、踏まえているそうな。「??」
旅の僧侶たち、川のほとりの御堂で、一夜を明かす。夜、松明を持った鵜匠が現れる。彼は、殺生禁断の禁制を破って殺された鵜匠の亡霊。鵜飼の技を見せたのち、暗闇へと消えてゆく。「それを踏まえた句なの?…お、おもたいね。」
2024.01.29.:
穂積駅から、岐阜駅まで、てくてく。
河渡 > 加納 | 加納 > 鵜沼